<前|
幼き日の友。己と瓜二つの友。その「あくがれ出た魂」を鎮めるため出雲の国をさまよった「ぼく」。紆余曲折の末に「小さな光」を「血も/凍るおもいで 両のて/のひらに そつと/すくい上げた」
そうして逃げるように東京に帰り「今これを書いている」。(「わが出雲(エスキス)」『倖せそれとも不倖せ続』(1973年、書肆山田))
本当にそうだろうか?
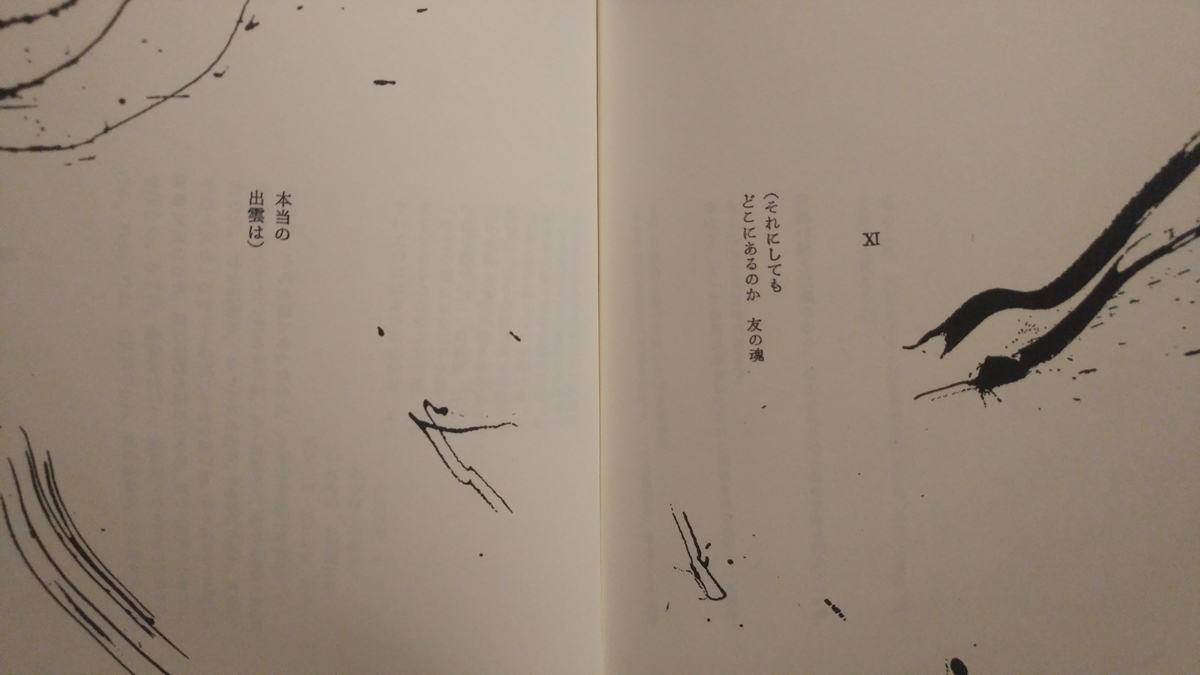
友の魂を求めて:往路
(それにしても
どこにあるのか 友の魂
本当の
出雲は)
――「XI」 『わが出雲』
一羽の首のないあおさぎが叫んで行つた
「教えてください あの人の魂は
どこにあるのでしよう 一体どこに
どこに どこに どこに どこに どこに」
そんなことが判るくらいならば……
――「VII」 『わが出雲』
『わが出雲』のメインストーリーは明白である。「わが出雲」=本当の出雲を探し、親友の魂まぎを為すこと。
何をしに出雲に来たのか。友のあくがれ出た魂をとりとめに来たのだ。わが友、うり二つの友。時間の、闇の中で、鳰鳥のようにほの白く笑う、若くして年老いた神。みずから放つた矢に当つて、喪山の藪かげにとり落され、見失われたという、その魂を。
――「II」 『わが出雲』
「ぼく」がいま立っている場所は求めている故郷ではないらしい。「この贋のふるさと」であり「すべてがすべてと入り混り、侵し合う、この風土」だ。
ふりかえれば、木綿かけた榊の裏で、血ばしつた目が、こちらをしきりにうかがつている。(それにしても、どこにあるのだ、わが出雲は。ことごとく、これは、贋の出雲)
――「IV」 『わが出雲』
「ぼく」の旅=地獄下りは様々なレベルで「すべてがすべてと入り混」ることにより、並々ならぬものになる。メタレベルでは「よせあつめ 縫い合わせれた国」であることを引き継いでいるわけだ。
この流れの中で、我々はいくつもの美しい幻覚を見る。
だまされてはならない、
群立つ雲のような
七巻き巻いた葛(かずら)のような、
この偽の出雲の
底知れぬ詐術に。
――「VI」 『わが出雲』
誰に会いたいのだ
何かがいま、月をすつかり隠してしまつた。
――「VII」 『わが出雲』
《何をしているんですか、あの水つぽい詩人は?》
キジ〔野原で〕
《探しているんです、もう何千年も前に失くしたものを
いまだに、性こりもなく》
ニワトリ〔庭先であざわらつて〕
《ケケロケケー》
――「VIII」 『わが出雲』
分かっているのだ。分かりきっている。
「わが出雲」も「友の魂」も、本当は存在しない。うり二つの友なんて「ぼく」には居ない。あなたにも。そのはずだ。
どこにもないから「何千年」も探すことができる。「不在」は「存在」の可能性を提供し続ける。それが絶対に不毛なものであれ。*1
月が隠蔽された夜の果て、「思いもかけず/気の狂つた母にぼくは出くわす」。《亡母憧憬》のモチーフだ。
「友の魂」が「そもそも存在しない」のに対し、亡き母は「今はもう存在しない」ものである。何重にも。
ポケットの中で櫛が二つに折れた。
《お母さん ぼくはあなたの死んでからの子だけれど
やはりあなたの子なんですから
遠からず 狂うはずです
たのしみです》
三度まで、飛びついて母を抱こうとしたが
母の姿はその度にぼくの手からぬけ落ち、
――「IX」 『わが出雲』
ここにおいて「実作者」の幼児期の記憶が参照される、と『わが鎮魂』は述べる。(注:傍線は引用者による。本来は傍点)
その声を追つて野に出れば、
十何万のがぜる群 角をふり立て ががががが、
十何万のがぜる群 角をふり立て ががががが。
――「IX」 『わが出雲』
十何万のがぜる群…… 幼時、母に連れられて、宍道湖北岸を走る電車ではじめて出雲大社へ行った時、車窓から見たいちめんの葉のない桑畑の印象。おそらく、私の作った唄めいた文句の、記憶にある限りで、最も古いもの。これをそのまま用いた。
――「IX」 『わが鎮魂』
「IX」はある意味旅の終着点と言える場所だ。後述するように旅人は、詩人は、これ以上先に進めない。
どん詰まりから/帰還の騙り:復路
行きはよいよい帰りはこわい。
ダンテ『神曲』は地獄篇・煉獄篇・天国篇の三部あるうち、地獄篇が一番引用されている。その長さゆえに天国篇までたどり着く人が少ない、というのは一つの事実であろう。しかし本質的に、人間は地獄「下り」にこそ魅力を感じるのではないか? 地獄下りはミームとして東西神話に織り込まれている。
帰還の物語、作品の終焉へと向かう動きはどうしても嘘くさくなる。これは作品が「自らの終わり」を記憶していないことに由来するのかもしれない。人が、突き詰めれば自らの死を知覚し得ないように。*2
次の「作品の始まり」に関する文章を思い出しても良いだろう。
作品たちは何を記憶しているだろう? 作者をだろうか? そんなはずはありえまい。作品におぼえていてもらった作者などありえたはずがない。だが、何か別のものを記憶していないはずもまたありえない。自分自身をか? いや、この答えは矛盾している。はじまりをか? 自分のはじまりを記憶の彼方へ消し捨てたときはじめて作品ははじまるのではないか。私が最初にいいたいのはそのような記憶でもない。作品はかれ固有のある記憶によってはじまる。自分がいなかったときの記憶によって。作品と記憶とのかさなりあいが、そのままで体現しているこのようなずれが、私たちへの、そして作品そのものへの、詩人の入場である。
今の問題は「詩人の退場」をいかに行うべきか、ということである。一つの処方箋は「作品が未完である」という印象を与えることだ。
幻想的作品がうさんくささから脱却する一つの道は、それが未完であること、あるいは未完であるという印象を与えること(この二つは、せんじつめれば、たぶん同じことだ)。
――「作品の廃墟へ 16」 入沢康夫『詩の逆説』(1973年、サンリオ出版)
例えば、カフカの未完成稿が未完ゆえに与える幻惑。宮沢賢治がその死まで作品を改作し続けたことを知ったあとの印象*3。連載小説の更新が突如途絶したために生じる空白の広がり*4。
帰還にあたって根源的な破綻が起き、その嘘くささが突き抜けてしまったのが『漂ふ舟』という作品になるのだが……。
「作品の廃墟へ」(1970年)の引用した部分は、ともすれば『わが出雲・わが鎮魂』(1968年)を念頭においているのかもしれない。
『わが出雲』における幕引きは明らかに失敗だった(と以下で主張する)。帰還のシーケンスは長編詩であるがゆえに生じたものだろう。構造上の特徴であり、今回の場合欠陥になってしまった。明確な完結への意志があったせいだろうか?*5
『わが出雲』「IX」の亡母憧憬は作品内の最も深いパートで、その後をどう持っていくべきか。実作者のペンの迷いを感じる。
そのとき、贋の出雲は、ぼくの前で、決定的に二重になり、三重になり、無数の姿を一時にさらけ出した。
(中略)
ぼくは、足の裏と、ひかがみと、腰と、みぞおちと、背と、頸と、頭と、それぞれに、ちがつた出雲を同時に感じた。
(中略)
とてつもなく巨きな星が、ぼくの頭のすぐ上に夢のように降りて来ては、舌うちして遠ざかつて行く。
(中略)
やがて、すべては風に吹きはがされる田舎まわりのプロレスのポスターのようにはがれ落ちて、
青黒い闇と沈黙の中へ、ひとしきりひらめきながら消えていつた。
――「X」 『わが出雲』
この、うそくささ。作品としての不出来。
作品が終わるためには幼児期の追憶から無理やり叩き起こし、「今ここ」へと焦点を戻さなければならなかった(まずこの急転の必要性がよく分からない)。その方法がセルフオマージュなのだが、しかし全く有効ではない。
特に「贋の出雲」という語句はいただけない(そう書くしかなかったとしても!)。「XI」の「本当の出雲」との対比だとして、実作者は「贋」と「本当」がもはや対比すべきものでなくなっていることに気付かなかったのか? 「VI」の最後から「IX」までの流れで、「本当」の不在性と同時に「贋」の不在性も示されていたのに(オリジナルが無いなら残った全てはオルタナティブで、翻ってオリジナルだ)。
もう少し突っ込むとこの二項対立の解消を「脱虚構」と読むこともできるが、コントロール不能に陥ること必至なのでその直前で本稿はとどまることにする。
https://wagaizumo.hatenablog.com/entry/2021/12/13/053815
ここはただ「出雲」と書けばよかった。「X」で存在を意図しながら「贋の」と書くことによって、ここまで丹念に構築して来た「虚構」のメタ構造が一段単純になってしまった、と感ずる。*6
余談。「X」以降、「ぼく」が途方に暮れるのと「実作者」が途方に暮れるのがダブってくる。
この一致は不幸の産物だ。『わが出雲』において「実作者」は迷宮の作り手なのだから、絶対に迷ってはいけなかった。作品に作者が負けている。
このあと「XI」が冒頭でも引用した「(それにしても/どこにあるのか 友の魂//本当の/出雲は)」。
そして
こう、こう、こう、と呼ばわつて、友の魂まぎ、友の魂まぎ、幾夜か寝つる。ついに、魂まぎかねて、途方にくれようとしたときに、雷鳴が起こつた。跳びはねる猪のように百の人穴にこだました。その人穴の一つからとび出してふり仰いで、ぼくはとうとう見つけたのだ。わが出雲を、そして友の魂を。(あの穴の奥で、仮の眠りをむさぼろうとしたときには、ぼくは確かに、誰かと道連れだつたのだが、それが誰であつたのか、どうしても思い出せぬ)
――「XII」 『わが出雲』
「雷鳴がおこつた」以降のテキストは全て嘘だ、と断言してもよい。あまりにも作品として求心力を欠いている。
あるいは、夢想にすぎない。それも、ネルヴァルがやってみせたような(夢と現の境を取っ払うような)本気の夢想ではなく、「仮の」夢想。ご丁寧に「仮の眠り」と書いてくれている。
どちらにせよ、読者の「「いいかげんなことではだまされないぞ」という態度(つまりうまくだましてほしいという熱望)」(「作品の廃墟へ 18」)を悪い方向へ裏切ってしまっている。
『入沢康夫論2-1』「余録1」ではここの植字的方法について触れた。再掲すると
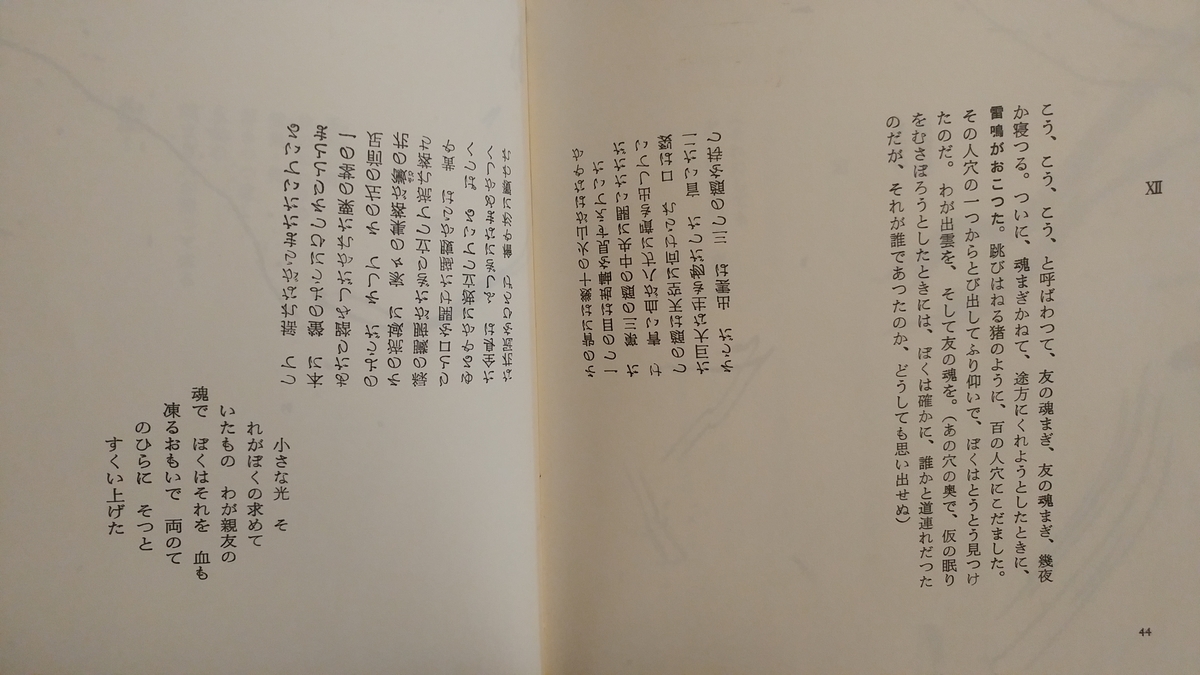
鏡文字も神紋の形もなんだか苦し紛れの工夫に見えてくる。
「わが親友の/魂」などという、そもそも存在しないものをどうやって「すくい上げ」るというのか? 別の何かと取り違えてはないか? この裏には結末へ向かうためのご都合主義・苦々しさが隠されていないか?*7
『わが出雲』の最後は、次のような詩句で締めくくられる。
毘売(ひめ)の埼(さき)
旅のおわりの
鴛鴦(おし)・鳬(たかべ)
浮きつつ遠く
永劫の
魂まぎ人が帰つて来る
意恵(おえ)!
――「XIII」 『わが出雲』
これは(自注にもあるように)次の引喩だ。
幻影の人は去る
永劫の旅人は帰らず
――「一六八」 西脇順三郎『旅人かへらず』(1947年、東京出版)
『わが出雲』において、旅人はどうも帰還を要請されているらしい。だから急場の「嘘」が必要だった?
追補。先に発表された「わが出雲(エスキス)」では発話者が東京の住まいに帰っていることが示される。それに比べると決定稿は帰還の直前といった風だ。オルフェウス・イザナギに倣えば、ここで振り向くと「ぼく」は「親友の魂」をとり落してしまうのだろう。
「うり二つ」「分身」である親友は同性と読まれることが多い(『わが鎮魂』もこの線である)。しかしオルフェウス・イザナギから逆回しして二卵性双子のような異性(幼児期に性差が顕現しない)と思うと、作品にエロティックな色が加わる。
Seagull Calls
出来の良くない部分をチクチク咎めてきたが、果たして何が言えるというのか。36-37歳の詩人の力量が至らなかっただけではないか。
けれども、実作者の意図(と推定されるもの)を越えてここから何か取り出せる気も僅かにする。特に『漂ふ舟』との関連において。
(前略)パロディのパロディを本文(もどき)と注(もどき)とで組み立て、こうすることによって詩の「反現場性」「自己浸蝕性」の問題を、無二無三に追い詰めてみることだった。つまり、私の力点は、「作品を成立させること」にでなく、「作品の成立とは何かを問うこと」にかかっていた。
――「あとがき」 『わが出雲・わが鎮魂』
実際はこれまで見てきたように、『わが出雲』は無理やりにでも「成立」しなければならなかった。
何故?
『わが出雲』の「エスキス稿」(として提出されたもの)との異同は次にまとめられている。
須賀 真以子「読むことの始源に向かって : 入沢康夫『わが出雲・わが鎮魂』における「わが鎮魂」の役割」
https://teapot.lib.ocha.ac.jp/records/34138
引き伸ばしのような「X」は決定稿で初めて加わった。最も深い「IX」と結末の「XII」はおそらく初期からあった。
『わが出雲』執筆時点の作者にとって、「XII」は幻想=物語の終わりとして不可分だったのだろう。(もしここで「虚構」に対する構造が一段深まればうさん臭さは解消されたのだろうが……しかし「IX」のあとで何ができたというのか?)
だが幻想的なものは、その本質場、どうしても物語(レシ)、そして語りと結びつかざるを得ない。
――「作品の廃墟へ 10」
いっぽう、いわゆる幻想的な作品における語りは、語り得ざる「幻惑」に対して、時間と形式のわくを課するという意味で、本質的な矛盾をはらんでいることは先にも言ったとおりだ。そして、この矛盾性は、その作品が単に大衆の好奇心や怪奇残酷趣味におもねることを目的として書かれるのではない場合、おそかれ早かれ、作品の常識的完結性を食い破らざるを得ないのではあるまいか。
――「作品の廃墟へ 13」 (引用者注:傍線は本来傍点)
こうして「未完(風)」という道を提示しておきながら、入沢康夫の作品にはどれも「完結」感がある。『牛の首のある三十の情景』は「幻想的作品」といってよいが、物語的というよりは空間的であり、しかし「恋情の中へと、ますます深くとらへられて行く」ことでちゃんとオチをつけている。
これを入沢の素質であり、誠実さであり、隙の無さであり、限界と言ってしまえばそうかもしれない。
入沢康夫論3 – 1:牛の首をめぐるパラノイアックな断章(前編) - 古い土地
あるいは「復路」において、完結性を装いつつ「罠」を仕掛けていたのか。
黄泉下りの物語において、往路とは獲得の過程であり、復路とは喪失の過程である。
そしてまた(「物語」=「幻想」と「現実」の二項対立を前提としてよいのなら)、物語の本質は獲得=往路であり、現実の本質は喪失=復路である。
復路のシーケンスは現実との接続のために行われ、ここに嘘くささが紛れ込む余地がある。つまりは現実の嘘くささであり、言語による分節で現実を捉えることの限界だ。*8
「復路」に従って「読者」は「現実」に帰る。それは導きなのか、心ならずもの旅なのか。
『わが出雲』から我々は「帰還」「幻想=物語=記憶の終わり」「身体的現実」「言語の限界」といったテーマを引き出した。
次回は入沢康夫論の終幕として『漂う舟』を参照しよう。誰にでも訪れる(らしい)「身体の終わり」のテーマを予告しておく。
「各自の死の必然的な到来の予想さへも、つひには忘れ去られるであらう。」(「牛の首のある七つの情景 6」)と書いた詩人は、だが皮肉るうちに本当に忘れていたのかもしれない。
その報いは如何ほどのものだったか。
鷗/カモメ/Seagullに見えたものは、本当はなんだったのか。
|次>
*1:このような「失われた半身」のモチーフはプラトン『饗宴』中の「愛の起源」に関する挿話を思い出させる。はるか古来、人は「2人で1人」であり、「男男」「女女」「男女(アンドロギュノス)」の3つの性があった。人の伸長を恐れた神がこれを分かち「男」と「女」の2つの性にしたのだが、分かたれた「半身」を求める気持ちが「愛」だと説明する。アンドロギュノスからは異性愛が、「男男」「女女」からは同性愛が生まれるらしい。
村上春樹『海辺のカフカ』では「大島さん」というLGBTQ界最強(?)のキャラクターが出てくるのだが、それに関連してかこの挿話が紹介された。https://yomidr.yomiuri.co.jp/article/20111128-OYTEW60908/
*2:死の不可知性について、例えば「未知生、焉知死」『論語―先進』
*3:https://wagaizumo.hatenablog.com/entry/2021/11/26/002653
*4:「小説家になろう」の登場によって作品の終わり方として「エタる」という形態が許されることを我々は知った
*5:長編詩の系譜でT.S.エリオット『荒地』を引き合いに出してもよいだろう。あれは詩の体を為していない草稿をエズラ・パウンドが添削し「完結」させたのだ。「V 雷の言ったこと」という再生=帰還のパートが有効なのは、明確な完結感とともに微かに編集前の未完感が想起されるから?
*6:「XI」は不在を意図しているので「本当の」と書いてよい。何なら「贋の」と書いてもよい。
*7:ボルヘス「八岐の園」『伝奇集』ぐらい幕引きの動きがとってつけたようだと逆に愛おしくなるのだが、意図してできることではあるまい。